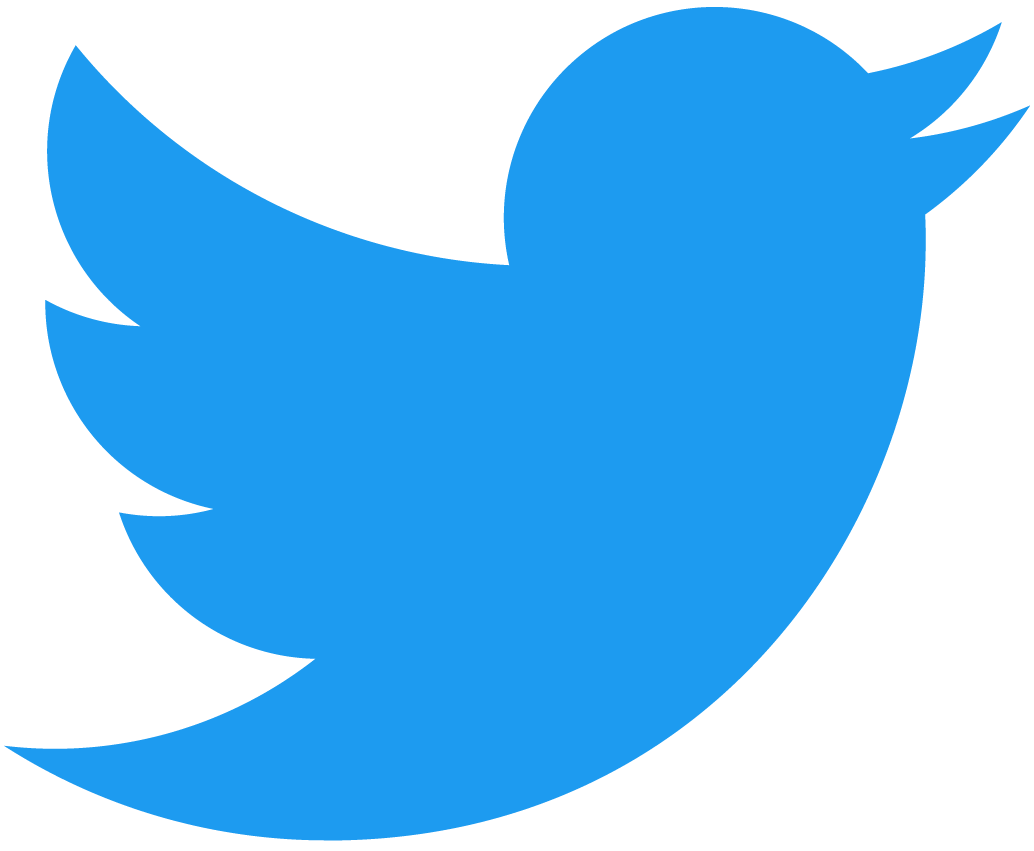あれは、ポケモン赤・緑がクラスを席巻し、テレビからはポケットビスケッツの曲が流れていた頃の話だ。
私は夏休みのほとんどを学習塾と、駅前のイエローサブマリンで過ごしていた。中学受験が終わったら「ケータイ」を買ってもらえる——それが唯一の希望だった。
その日も、SAPIXの宿題を終えてリビングで「デーモンの召喚」をスリーブに入れていたとき、母が何気なく言った。
「来週、会津に行くわよ」
福島県に住む母の古い友人の家に行くという。その家には、私と同い年くらいの男の子がいるらしい。
母は「ぜったい仲良くなれる」と言ったが、私は行きたくなかった。もちろん断れない。
そして、揺れに揺れる磐越本線の車内で、私は盛大に吐いた。
玄関から現れたのは、痩せた少年とその母親だった。
少年は私より少し背が高く、メガネをかけている。以後、彼をガリメガネ君と呼ぶことにする。
「ふだりでゲームでもしてきらんしょ? あとでおやつ持ってぐがらね」
ガリメガネ君の母の言葉には、はっきりとした東北訛りがあった。母親二人は居間に消え、残されたのは私たちだけ——“あとはお若いふたりで”とでも言いたげな空気。
無言のまま、ガリメガネ君は私を自室へと案内し、プレステの電源を入れた。
いつものあの不気味な起動音。見覚えのないタイトルが浮かび上がる。
「シーバス・フィッシング2」
彼は迷いなく釣り竿とルアーを選び、竿を投げ、待ち、竿を上げる。
魚がかかる。逃げられる。ルアーを変える。
投げる、待つ、上げる——その繰り返し。
画面の端には魚群探知機のような点々や、天候を示すグラフが映っている。
彼は一度も私に視線を向けず、ただ淡々と釣り続けていた。これは二人でやるゲームではない。
それでも、これが彼なりの「一緒にゲーム」の答えなのだろう。
静かな部屋に響くのは、コントローラー一台分の操作音だけ。
私は川で釣りをしたことはないが、きっと本物のシーバス釣りもこんな退屈なのだろう。竿を持たない私は湖面を見ているだけだった。
——塾の宿題でも持ってくればよかった。
やがてガリメガネ母が現れ、ハッピーターンとキャラメルコーンを盆に乗せて置いた。
「としゆきくんにもゲームやらせでやれ。せっかぐ会津さ来たんだがら」
その言葉を残し、無機質な視線で私たちを見下ろして去っていった。
ガリメガネ君は、おもむろにコントローラーを差し出す。
私は戸惑う。(え、私が?)
彼は、私がこのゲームを説明なしで遊べると思っているのか。
それとも「遊ばせた」という既成事実だけを作りたいのか。
沈黙の圧力に耐えきれず、私は◯ボタンを押す。何も起こらない。
×ボタンを押す。見知らぬ設定画面が現れる。細かい文字と図。背中にじっとりと汗がにじむ。
そして——私の耳元に、ねっとりとした声が落ちた。
「塾で勉強してるくせに馬鹿だな」
その声には、確信と優越感があった。
不思議なことに、私が感じたのは悔しさよりも寂しさだった。
人はそれぞれ、自分の中の「世界」を持っている。
ある場所で通じる価値も、その外では意味をなさない。
この部屋では「シーバス・フィッシング2」ができることが価値であり、それ以外は無意味なのだ。
他者との共存は幻想だ。人は本質的にわかり合えない。
その寂しさを本当に理解したとき、人は大人になる。
人はみな、それぞれの孤独を抱え、それぞれの釣り竿を下ろし、人生を終えていく。
——その日、私は一匹もシーバスを釣れなかった。
玄関でガリメガネ親子に別れを告げた。彼の表情はもう思い出せない。
おそらく二度と会うことはないだろう。私はSAPIXに通い、彼は自宅で釣りを続ける。
夕暮れ、新幹線の窓から見た街並みは真っ赤に染まっていた。
きっとどこかの家庭で、今日もプレステが起動音を響かせているのだろう。
私は、車内で小さく吐いた。