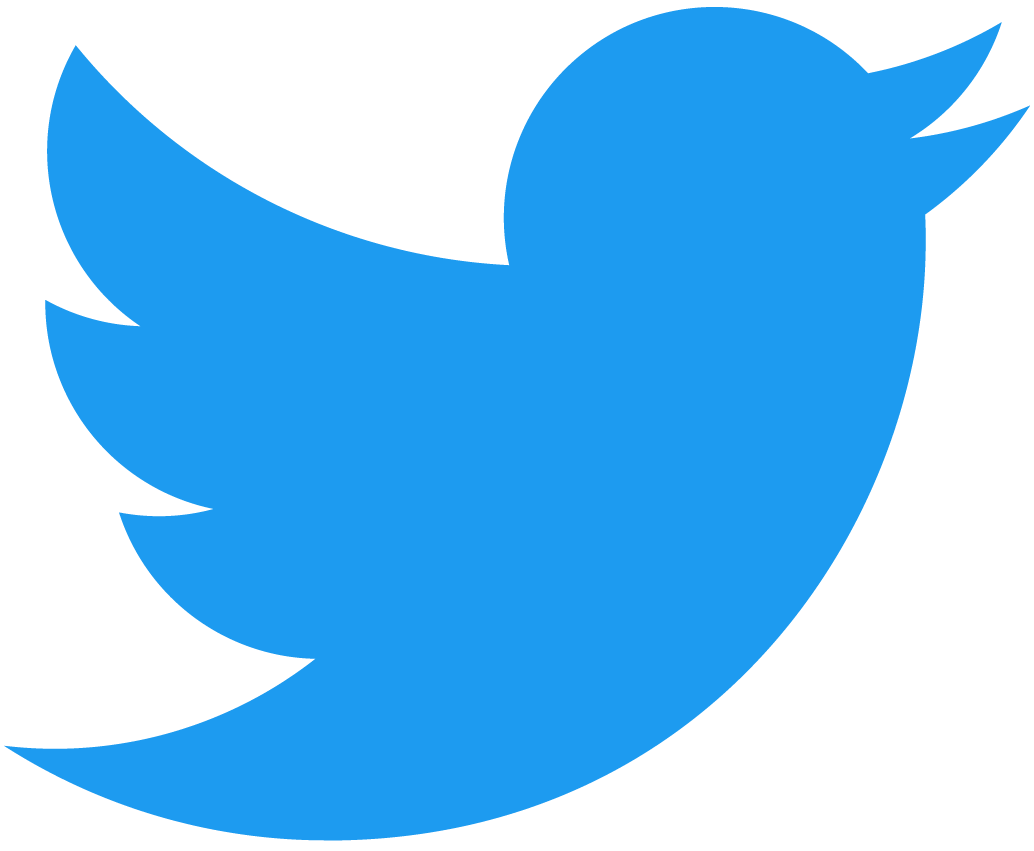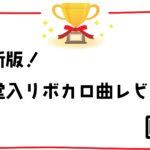『おもんない釣りゲーム / 神様うさぎ』
あれはちょうどポケモン赤・緑が大ヒットし、ポケットビスケッツにクラスのみんなが夢中になっていた頃の話だ。
私は夏休みのほとんどを学習塾と駅前のイエローサブマリンで過ごし、中学受験が終わったら「ケータイ」を買ってもらえることを夢見ていた。
SAPIXの宿題を終え、リビングでデーモンの召喚をスリーブに入れていたとき、
「来週会津に行くわよ」と母が言った。
福島県にある、母の古い友人の家に遊びに行くのだという。
その家には私と同い年くらいの男の子がいるので、”ぜったい仲良くなれる”と言う。
行きたくないが、断ることはできなかった。
揺れ動く磐越本線の中で私はゲロを吐く。
-----------------------
玄関からは痩せ細った少年が母親と一緒に出てきた。
彼の背格好は私より少し高く、メガネをかけている。(以降:ガリメガネ君)
「ふたりでゲームでもしてきたら?あとでおやつ持っていくわね。」
ガリメガネ君の母が言った。その言葉のイントネーションに違和感を感じる。東北の訛りだ。
母親二人は居間に消えていく。
子供二人は置き去りにされた。あとは”お若いふたりで”といった感じ。
ガリメガネ君は無言で私を自室に導き、プレステの電源を入れた。
いつもの不気味な起動音、見覚えのないゲームのタイトル。
「シーバス・フィッシング2」
画面が移り、彼は黙々と釣り竿とルアーを選ぶ。私は無言でそれを見つめる。
ガリメガネ君が
竿を投げる。
待つ、、、、
竿をあげる。
魚がかかる、、
逃げられる。
ルアーを変える。
竿を投げる。
待つ。。
竿を上げる。
また投げる。
待つ。
を繰り返していく。画面の端には魚群探知機らしい点々や天候を表すグラフなどが写し出されている。
彼は私に目を向けることなく、黙々と釣りをしている。
これは2人でやるゲームではない。
だが、これが彼にとっての「ふたりでゲームでもしてきたら?」へのアンサーなのだ。
静かな部屋にコントローラー一台分の操作音が響く。
私に川で釣りをしたことがなかったが、きっと実際のシーバス釣りもこんな感じなんだろう。
釣り竿を持たない私はじっと湖面を眺めていた。こんなことになるなら塾の宿題を持ってくればよかった。
しばらくして、ガリメガネ母がおやつを持って入ってきた。
我々を見下ろす無機質な目線。普段客には見せない、内向きの母モードだ。
「としゆきくんにもゲームやらせてあげえ。せっかく会津さ来だんだから」
ハッピーターンとキャラメルコーンが乗った盆を置き、言い捨てるように出て行った。
ガリメガネ君は
おもむろにコントローラーを私に渡した。
無言のガリメガネ君。
私は困惑した。
(え?私が、、やるの?)
まさか彼は、私が「シーバスフィッシング2」を説明なしでプレイできると思っているのか。
または、「ゲームをやらせた。」という事実を作るために、プレイできないことはわかっていながら、型式的にコントローラーを握らせたのか。
私は彼の無配慮を嘆いた。
沈黙。。
私はガリメガネ君の刺すような視線に耐えきれず、とりあえず「◯」ボタンを押す。
、、何も起こらない。
「×」ボタンを押してみた。
画面が変わった。細かい文字や図が羅列した見覚えのない画面。
冷や汗と時間がゆっくりと流れる。。。
そして、私の左耳に粘着質な声が届いた。
ーーー「塾で勉強してるくせに馬鹿だな」
自信と確信に満ちたガリメガネ君の声だった。
意外にも、私がそのとき感じたのは悔しさよりも”寂しさ”であった。
人はそれぞれのコミュニティで独自の文化を形成している。ある共同体の中では通用する認識や行為もその外側では無意味だ。
この部屋では「シーバスフィッシング2」ができることが「価値」であり、それ以外の能力は無意味なのである。
==他者との共存は幻想だ。他者は本質的にわかり合えない存在だ==
私はそんな寂しさを感じた。
そして、その寂しさを本当に受け止めたとき、人は大人になるのだと思った。
人はみなそれぞれの孤独をかかえながら、それぞれの釣り竿をおろし、人生を終えてゆくのだ。
その日、私はシーバスを一匹も釣れなかった。
-----------------------
私は玄関でガリメガネ君親子と別れた。彼の表情は覚えていない。
恐らくもう会うことはないだろう。私はSAPIXに通い、彼は自宅でシーバスを釣る。
夕刻、私は東京へ向かう新幹線の車窓から、流れゆく街並みを見た。真っ赤に染まっている。
きっと、どこかの家庭でいまも、それぞれのプレステが起動音を上げているのだろう。
私は車内で小さく嘔吐した。